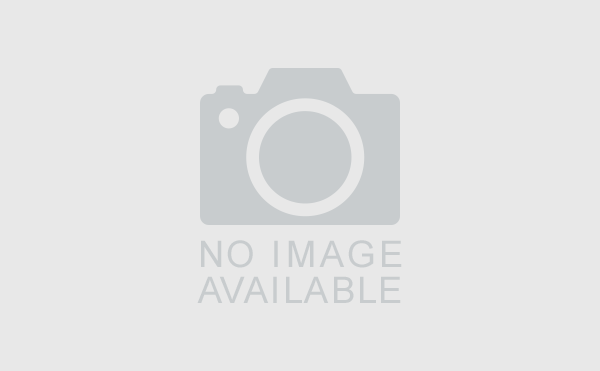【連載「学級経営診断ツールが学級を変える」】はじめに
退職して7年。この間、民間企業と一緒にICTを学校教育に取り組むプロジェクトに参加してきた。
今年、それも一段落した。
ふと気が付けば、70歳も目の前に迫ってきた。
大分時間にも余裕ができたし、その時間を利用しながら、今一度若い先生方に役立つ情報を発信したいなと思うようになった。
授業に関して言えば、私はそれほど上手とも言えない。
授業に関する情報はあきらめて、私が若い時から考え、実践してきた学級づくり、学級経営のことについて発信してみることにした。
今回、とりあえず10回余りの連載としたい。
以下が、そのタイトルと小見出しである。
連載タイトル案と小見出し(全10回)
第1回:学級経営を問い直す:退職教員から若い教師への提言
- 私が学級経営を問い続ける理由
- 学級診断ツールとは何か?一連の取り組みを理解する
- 遊びを学級経営に組み込むことで何が変わるのか
- 2軸診断票で学級の現状を把握し、改善へ向かう第一歩
- 若い教師へ伝えたいこと
第2回:学級は偶然ではなく計画的に作るもの
- 計画的な学級経営の必要性とは
- 診断票を活用し、安定と成長のバランスを分析する
- 4象限のどこに学級が位置づけられるかを可視化する
- 「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」を学級設計へ落とし込む
- 実践後のフォローアップとさらなる発展へのプロセス
第3回:向山洋一が提起した「自由で平等な場からの出発」とは
- 向山洋一が示した学級経営の出発点
- 「自由」と「平等」をどのように学級文化へ根付かせるか
- 診断ツールを活用し、自由と平等の状態を測定する
- 遊びの要素を活用しながら、自由と平等を体験的に学ぶ方法
- 診断データを基に、学級経営の改善策を議論し実行する
第4回:学級経営の最大の課題:子どものつながりはなぜ弱くなったのか
- SNSが子ども同士の関係に及ぼす影響
- 学級診断ツールで関係性の質を測定し、可視化する
- 「遊び」の要素がつながりを強化する理由とは?
- 教師集団で討議し、より実効性のある対策を決定する
- 実践後の変化をフォローし、さらなる改善へつなげる
第5回:学習意欲を引き出す授業づくり:面白い授業の本質を考える
- 「面白い授業」とは何か?誤解されるポイント
- 診断ツールで授業の質を評価し、課題を見つける
- 授業の対話性や知的挑戦度を2軸で分析する
- 「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」を授業デザインへ組み込む方法
- 実践結果をフォローし、授業の質を継続的に向上させる
第6回:教師は一人で学級を抱え込むな:チームとしての学級経営
- なぜ教師が負担を抱え込みやすいのか
- 診断ツールで教師の業務負担を分析する
- 「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」を活用した役割分担の工夫
- 教師集団で改善策を討議し、チーム運営へ移行する方法を考える
- 実践を通じて、学級経営のチーム化の効果をフォローする
第7回:学級経営の診断:問題を可視化し、成長を促すツールの活用
- 学級の状態をデータで把握する重要性とは
- 2軸診断票とグラフ化による学級の可視化手法
- 「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」を診断結果と組み合わせて活用する
- 教師集団によるヒアリング・討議を通じた改善策の決定
- 診断結果と実践データのフォローによる継続的改善
第8回:学級経営とICT:負担を減らし、成長を加速させる仕組みづくり
- 教育現場におけるICT活用の現状
- 診断ツールとICTの統合による学級管理の効率化
- 「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」をICT活用の中に取り入れる
- 教師集団のオンライン討議による学級経営の最適化
- ICTと診断ツールを活用した学級経営の未来
第9回:退職教員が考える「学級経営の未来」:これからの教育に必要なもの
- 私がこれまでに見てきた教育の変遷
- 診断ツールを活用したデータ主導型学級経営の可能性
- 「遊びと学びの融合」を未来の学級経営へどう組み込むか
- 教師集団の討議を通じて、学級経営の未来を考える
- フォローアップとデータ活用による持続可能な学級づくり
第10回:学級経営は教育の本質:若い教師へのメッセージ
- なぜ学級経営は教育の中心なのか
- 診断ツールを活用することで、学級経営の質を向上させる
- 「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」を学級文化として確立する
- 教師集団による継続的な討議と実践フォローの重要性
- 若い教師に求められる「データと協働による学級づくり」の視点