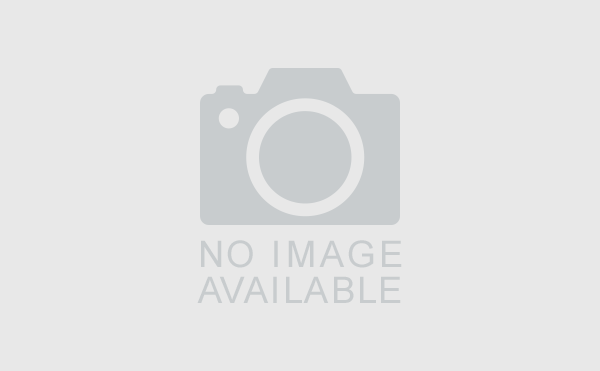【雑感】知的学級集団づくりとは何であったのか
この歳になってくると過去を思い出すこと、振り返ることが多くなる。
私としては、どんな歳になっても前を向いていたいという思いがある。
過去を振り返るにしても、その「過去」は前に向いているものなのかが大切なことだ。
人の役に立つのか、今の問題を解決にしていくのに何らかの参考になるものなのか。
私の教師人生にとって、エポック的な出来事は知的学級集団づくり研究会を立ち上げたことだ。
仲間に支えられながら、全国的な組織にしていこうとしたものである。
知的学級集団づくりとは何であったか。
知的学級集団づくりは、学級を単に知識を教える場所として捉えることではない。
子供一人ひとりが主体的に思考する。
創造性を発揮する。
互いに協力しながら知的プロセスを共有する。
子供の自己実現を支援しながら学級全体の成長を促進することを目標としていた。
そのために、学級集団として学び成長する環境を形成することを目指すものであった。
知的学級集団づくりの基盤は、向山洋一氏の「自由で平等な場からの出発」という実践研究レポートの教育理念・教育方法である。
ここにあったのは、向山洋一実践に対する強烈な憧れである。
教育雑誌、教育書を読む。
それも一冊や二冊ではない。
毎月何誌もの教育雑誌を定期購読し、何冊も教育書を読む。
その中に出てくる「向山洋一」という教師、そして氏のもとで学んでいる子供たちの姿。
それは私を惹きつけてやまないものだった。
教師としての力も子供たちにとって魅力もない若造が、もしかしたら
「自分でも教師をやっていけるかもしれない」
と思ったのが「向山洋一」を知ったことであった。
向山学級は、「管理された子供たち」ではなかった。
一人一人が自分の脳みそを精一杯に働かせ、生き生きと活動していた。
同じ日本の子たちなのに、何故自分の学級とは違うのか。
それを思った時、子供たちに申し訳ないと思った。
保護者に申し訳ないと思った。
少しでも「向山洋一」に近づきたいと思ったのである。
強烈な憧れが、私の学びの原動力となった。
私の中に学びが蓄積されていく。
蓄積されていけばいくほど、誰かと共有したい。
誰かと話し合ってみたい。
それが学校外の研究大会への参加、そしてサークル立ち上げへとつながっていく。
教育書・教育雑誌にあった魅力的な実践をすぐに試してみる。
未熟な私でもやれる。
何より教室の子供たちが変わっていく。
毎日が楽しい。
朝、車で学校に行くと子供たちが駐車場で待っている。
私の車を見ると追いかけてくる。
車から降りると、子供たちが私の荷物を持ったり、手を握ってくる。
休み時間になると、私が教室の事務机に座っていると子供たちが集まってきた。
私の机の周りは、いつも二重に子供たちが取り囲んでいた。
子供たちと話すことが楽しかった。
教師として幸せな日々だった。
私の心の中には、
「これは私の力ではない。多くのすぐれた先生方、特に向山実践を真似しているから実現できているのだ」
という思いがあった。
学級全体が変わりだすのは、授業もそうなのだが、私にとって大きな影響を与えたのが1972年に全国教研で向山洋一氏が発表した「自由で平等な場からの出発」である。
このレポートのおかげで、私は見通しを持った学級づくりができるようになったのである。
それが知的学級集団づくりへとつながっていくのである。