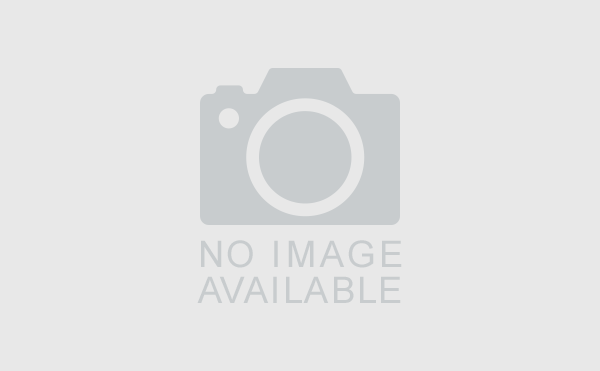【雑感】一斉授業は「古臭い授業」なのか
それは、社会科、単元の導入時だった。
子供たちは、これから学習していく内容に関する知識について、多くを知っている子もいれば、ほとんど何も知らないと思われる子もいた。
レディネスの違いである。
これは「普通の学校」であれば、どこでも見られる状況である。
若い教師は、様々な子がいるので、これからスタートする学習が効果的に、そしてどの子もが意欲的に参加するようにある程度「土台」を揃えたいと思った。
そこで、授業の第一時。
一斉授業の形で授業をすることにした。
子供たち全員が黒板の方を向き、教師の話に集中できるような学習形態にしたのである。
教師は、授業が始まるとおもむろにある「モノ」を取り出して、子供たちに問いかけた。
「これは何かわかるかな?」
もうそれだけで、子ども達は興味津々である。
そのとき、たまたま視察に来ていた教育委員会の方と案内していた校長が廊下を通った。
廊下から授業の様子を眺め、その教室を通り過ぎて行った。
視察終了後、校長室で教育委員会の方が校長に
「まだまだ古臭い授業もありますね。教師は教えるのではなく、ファシリテーターに変わらないといけませんよね。」
若い教師の授業をそのようにコメントしたのだという。
単元として実践していく。
そのプロセスの中では、一斉授業の形態もあるだろうし、グループ学習や個別学習もあるだろう。
時たま見た授業が、教師が前に立って、子供たちに教えていた。
そのことのみをもって「古臭い授業」とコメントしてしまう。
私のとらえ方が間違いでなければ「今の教育」は、一斉授業を否定はしていない。
主体的な学習活動の土台となりうるなら、そして効果的とするなら、教師は必要な基礎知識や概念を一斉授業という形で教えることもある。
「主体的・対話的で深い学び」における教師は、学習プロセスを円滑に進めるために、必要に応じて知識を効果的に伝える重要な役割を担っているはずである。
それがなければ「這いまわる実践」になる懸念さえある。
「上の方」のコメントやアドバイスが、現場で誤解を生み、意欲的な実践を摘んでいってしまっている。