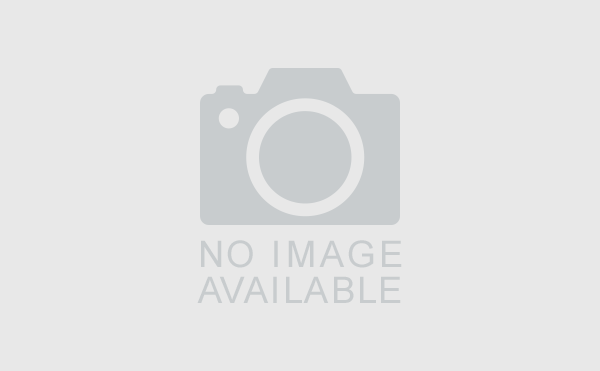【雑感】「特定の指導方法」を実践してはいけないのか
「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」(答申)の中に
誤解が生まれる一文がある、と私は考えている。
それが次の一文である。
「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、特定の指導方法のことでも、学校教育における教員の意図性を否定することでもない。
これを一読すると、「特定の指導方法をしてはいけない」と考える方がいる。
「〇〇方式」だとか「〇〇型」だとかの「特定の指導方法」を、「主体的・対話的で深い学び」を実現するためにはしてはいけない、と解釈するのである。
日本語の否定表現は、文脈によってその意味する範囲が変わることがある。
日本語の否定表現には2つある。
「完全否定」と「限定否定」である。
「これは鉛筆ではない。」(これは、完全に鉛筆ではない。鉛筆とは違う全く別のものだ)という「完全否定」である。
「タブレット端末はiPadだけではない。」(iPadはタブレット端末だが、iPadだけがタブレット端末というのではない)とする「限定否定」である。
「特定の指導方法でもない」という部分は「完全否定」なのかそれとも「限定否定」なのか。
読み手にとって「完全否定」と捉えられてしまうのか。それとも「限定否定」と捉えるかによって誤読が生じる原因となる。
もし、「完全否定」と誤読してしまうと
「主体的・対話的で深い学び」を実現しようとするなら、特定の指導方法を実践してはいけない。
という解釈が生まれることになる。
この誤読が現場には蔓延しているのではないかと思う。
しかし、本来の意図である「限定否定」と受け取るならば
「主体的・対話的で深い学び」の実現には、特定の指導方法だけが全てではない。特定の指導方法も有効な手段だが、それだけに限定して考えるものではない、となる。
そう考えることで、現場の教師の授業改善に向けての工夫や努力を尊重しているという意味が強くなる。
それなら何故「完全否定」ではなく「限定否定」と読み取ることができるかだ。
答申文の中から現場の教師たちの工夫や努力を認め、「主体的・対話的で深い学び」の実現に寄与してほしいという願いが繰り返し述べられる。
例えば次のように。
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善は、単なる「アクティブ・ラーニング」の導入にとどまらず、各学校の教育目標や児童生徒の状況、各教科等の特質を踏まえ、教師一人一人の専門性や創意工夫の下、これまで培われてきた我が国の教育の良さも生かしながら進められるべきものである。
このように、答申は特定の指導方法への一辺倒な転換を求めるのではなく、教師一人ひとりの専門性と工夫を尊重し、これまでの教育で培われた良い点を生かしつつ、新しい学びの視点を取り入れることで、より質の高い教育を「実現」してほしいという、現場への期待と励ましのメッセージを送っている。
「限定否定」であるもう一つの理由。
この一文の後半には、「学校教育における教員の意図性を否定することでもない」と続く。
「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、特定の指導方法のことでも(A)、学校教育における教員の意図性を否定することでも(B)ない。
ここでAとBが並列に否定されている。
ということは、もし「特定の指導方法ではない」が完全否定(「やってはいけない」)を意味するならば、「特定の指導方法をやってはいけない」という極端な主張と、「教師の意図も否定しない」という主張が並ぶことになる。
教師が授業を設計する「意図」の中には、当然、特定の指導方法を選ぶという意図も含まれる。
そうであるなら、特定の指導方法を完全に否定しながら、教師の意図は否定しないというのは、矛盾である。
しかし、これが限定否定(「それだけが全てではない」)を意味するなら、「『主体的・対話的で深い学び』は、特定の指導方法だけがすべてではないし、かといって教師が何も考えずに放任するわけでもない」という、非常に筋の通ったメッセージになる。
これは、「形だけを真似するな」というメッセージと、「教師は責任を持って学びをデザインしろ」というメッセージの両方を伝えており、これからの教育のあり方を包括的に示していることになるのである。