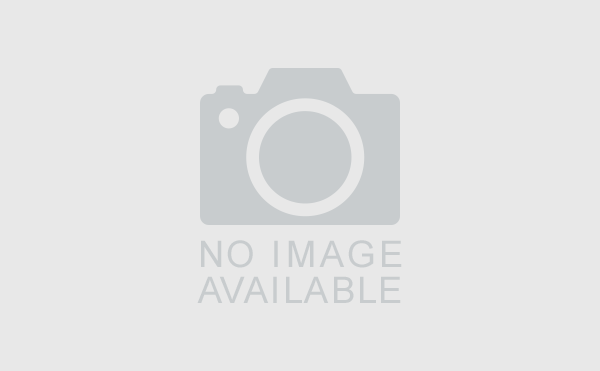【連載「学級経営診断ツールが学級を変える】第2回:学級は偶然ではなく計画的に作るもの
1. 計画的な学級経営の必要性とは
大学を出て、私はすぐに担任をした。5年生担任である。大学で学級経営について学んでいたわけではない。教師としての、担任としての考えや在り方を学んでいたのではない。素人同然の教師が何も知らずに子供の前に立つのである。それは何故可能だったのか。教師というのは、子どもと悪戦苦闘しながら、成長していくのだという今から思えば何とも善良な考えである。そして、それはその時代の教育に関わる多くの人たちが抱いていた信念にも近いものである。
「教師は子供とともに成長する」というのは間違いではない。しかし、だからと言って「学級は時間の経過とともに成長する」のかと言ったら決してそんなことはない。学級は偶然に成立するものではない。教師が意図的・計画的に設計し、適切な環境を整えることで、安定しながら成長する場となる。これは単なる管理ではなく、学級の構造を戦略的に構築することを意味する。
学級経営の中心となるのは、
| 安定のためのコミュニケーションづくりと成長のためのシステムづくり |
のバランスである。このことが長年教師として勤めてきた私の学級経営の主張点であり、肝である。学級が安定しなければ、子どもたちは安心して学ぶことができない。しかし、安定だけでは停滞が生じるため、成長のための仕組みを意識する必要がある。
さらに、現在の教育の状況、例えばいじめや不登校に代表されるような問題を考えた時にどうしても欠かせないと思った考え方がある。それは、学級経営には「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」の視点が欠かせないということだ。学びの場に遊びの感覚を加えることで、子どもたちは楽しみながら知的好奇心を高める。本稿では、学級診断ツールを活用しながら、計画的な学級づくりの方法を具体的に紹介する。
2. 診断票を活用し、安定と成長のバランスを分析する
意図的・計画的な学級経営の第一歩は、学級の現状を正しく把握することである。教師の直感や経験だけでは、学級が持つ強みや課題を客観的に分析することは難しい。そこで、学級診断ツールを活用し、データに基づいて評価を行う。
学級診断票の概要
学級診断票は、安定のためのコミュニケーションづくりと成長のためのシステムづくりの2軸を構成要素とした項目で設計され、50問(概略版は20問)の質問紙として作成される。教師がこれに答えることで、現状の学級の状態を診断し、課題を明確化することができる。
この診断では、以下の観点が評価される。
安定のためのコミュニケーションづくり
- 子ども同士の関係性(協力・対話・信頼)
- 教師・保護者との信頼関係(安心感・指導の受け入れ度・協働)
- 心理的安全性とトラブル対応力(安心して発言・行動できるか/対立・問題の解決スキル)
- 学級の協調性と地域・社会とのつながり(班活動・学級運営への積極性/地域・社会との関係性)
- 学習環境のデジタル化と情報共有(ICTの活用・学級情報の透明性)
成長のためのシステムづくり
- 学習環境の整備(挑戦機会・知的刺激の多さ)
- 自律的な学習と社会への接続(自己調整力・学びへの責任/学校・地域との連携)
- ルールの適応性と学級経営の柔軟性(自主性の発揮・柔軟な対応/学級運営の持続性)
- チャレンジの機会と評価のデータ化(困難への挑戦・失敗からの学び/データ活用による評価)
- 「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」の仕組み(遊びを通じた知的成長)
3. 4象限のどこに学級が位置づけられるかを可視化し型分けする
診断結果を分析するために、2軸のグラフを用いて学級を可視化し、4象限に分類する。これにより、学級の現状が明確になり、どのような対策が必要かを判断しやすくなる。
学級の4象限とその型
- 「理想型(安定 × 成長)」
- コミュニケーションが円滑で、子どもたちが主体的に学び、挑戦できる学級。
- 例:「協働が自然に生まれる学級」「学び合う文化が根付く学級」
- 「挑戦型(不安定 × 成長)」
- 子どもたちが意欲的に学ぶが、関係性がまだ十分に強くない学級。
- 例:「知的好奇心は旺盛だが協力が不足する学級」「個々の努力が目立つ学級」
- 「安定型(安定 × 停滞)」
- 学級は落ち着いているが、新しい挑戦が少なく、成長の機会が不足している学級。
- 例:「落ち着いているが刺激が足りない学級」「守りの学級」
- 「混乱型(不安定 × 停滞)」
- コミュニケーションが不足し、学級としてのまとまりや成長が難しい状態にある学級。
- 例:「方向性が見えにくい学級」「信頼と挑戦の両方が不足している学級」
この分析を通じて、学級の現状を明確にし、適切な改善策を講じることができる。
4. 「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」を学級設計へ落とし込む
学級の安定と成長を促すには、子供たちが「学級は楽しい。友達と学ぶことが楽しい」と思えるような学級経営である必要がある。そのために「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」の考え方を学級の設計へ組み込むことが不可欠である。学びの場に遊びの感覚を加えることで、子どもたちは主体的に学級運営へ関与するようになる。
5. 実践後のフォローアップとさらなる発展へのプロセス
学級診断ツールを活用して改善策を実施した後は、その効果を測定し、必要に応じて調整することが重要である。
フォローアップの具体的な方法は以下の通り。
- 再診断 → 実践後、学級診断ツールを再度活用し、改善されたポイントを確認する
- 討議と改善 → 診断結果を基に、同僚や尊敬できる教師からアドバイスを受けながら、さらなる改善策を検討する
- 定期的な振り返り → 学級の状態を定期的にチェックし、戦略的に調整していく
このプロセスを繰り返すことで、学級は持続的に発展し、より豊かな学びの場となる。