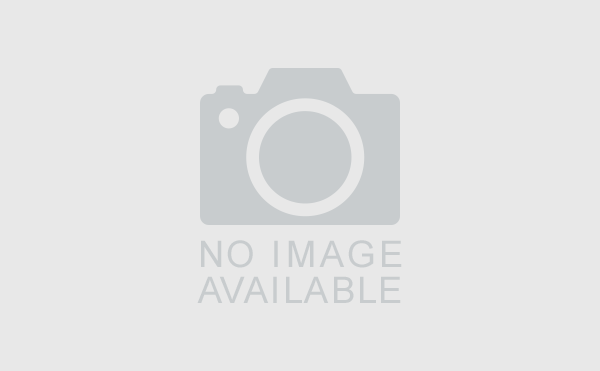【連載「学級経営診断ツールが学級を変える」】第1回:学級経営を問い直す:若い教師への提言
1. 私が学級経営を問い続ける理由
私は教員として37年間、一般職や管理職として、教育に携わる立場が変わる中で、学級経営のあり方を考えてきた。
日々の学級は、教師と子供が織りなすドラマの集積である。そこには偶然性というものが存在するが、決して学級は偶然だけで成り立つものではない。教師が意図的・計画的に環境を設計し教育活動を構想し、子どもたちが主体的に学べる場を築くことで、学級は安定し、成長する。
特に、安定のためのコミュニケーションづくりと成長のためのシステムづくりという2軸を意識することが重要であると私は考えている。
若い教師にはこの視点を持ち、戦略的に学級経営を進めてほしいと願っている。本連載を通じて、その具体的な方法を共有し、学級の質を向上させるための実践的なアプローチを紹介していく予定である。
2. 学級診断ツールとは何か?一連の取り組みを理解する
今の時代は、生成AIが飛躍的に向上している。この生成AIを活用して学級診断ツールを作成する。学級経営の質を向上させるために、この学級診断ツールを活用する。このツールは単なる測定方法ではなく、以下の一連の取り組みを指す。ちなみにこの学級診断ツールは私が構想し、そのアイディアをもとに生成AIによって細部を構築していっている。
- 2軸診断票で学級の状況を評価(安定のためのコミュニケーション / 成長のためのシステム)
- 診断結果をグラフ化し、学級を可視化(4象限に分類)
- 学級の現在位置を確認し、改善策を明確化
- 生成AIのみならず、同僚や尊敬できる教師からアドバイスを受けながら、実効性のある対策を教師自身が主体的に決定
- 実践結果をフォローし、さらなる改善へつなげる
この診断ツールを用いることで、学級の課題を明確にし、教師が効果的な対応策を打ち出すことができる。
3. 遊びを学級経営に組み込むことで何が変わるのか
これからの学級経営を考えるにあたって、もう一つ大切なポイントがある。それは、子どもの生活の中心である学級が楽しくなければならないということだ。そのために私は「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」という考え方が必要だと考えている。その在り方が学級経営の質を大きく左右する。遊びを単なる娯楽ではなく、学びを深めるための戦略的な手法として活用することで、子どもたちは学級という生活の場を楽しく感じ、主体的に学級運営へ関わるようになる。
例えば、学級診断ツールで「学級のまとまりが弱い」「学習への意欲が低下している」と診断された場合、遊びの要素を組み込むことで改善できる。
- 協力型ゲーム(子ども同士が課題解決を通じて関係を強化する)
- 探究型プロジェクト(学びを「遊び」に近づけることで興味を引き出す)
- ロールプレイ活動(子どもが楽しみながらルールを理解し、学級を運営する)
こうした活動を学級のシステムとして組み込むことで、学級経営の質が向上し、子どもたちが主体的に学級を作る意識を持つようになる。
4. 2軸診断票で学級の現状を把握し、改善へ向かう第一歩
学級経営を成功させるためには、まず学級の状態を正しく把握することが重要である。「感覚」ではなく「データ」で学級を評価し、実践的な改善策を講じるために、学級診断ツールを活用する。
学級診断では、以下の2軸で状況を分析する。
- 安定のためのコミュニケーションづくり(子ども同士の関係性、教師との信頼関係、対話の質等)
- 成長のためのシステムづくり(学習環境の整備、挑戦機会、学級運営への主体的な関与等)
この2軸で学級を診断し、学級の状態をグラフ化することで、「安定しているが成長機会が少ない」「成長の機会はあるが安定性が不足している」といった具体的な課題を特定できる。
ただし学級診断結果だけでは十分ではない。それはただ単に数値化して可視化しただけの話で、結果の裏側に潜む要因をできるだけ多くの知恵を集めて考えることが必要である。医師が問診票だけで診断しないのと同じである。学級経営であれば、学級経営診断結果をもとに、同僚や尊敬できる教師からアドバイスを受けながら、実効性のある改善策を決定していくことである。そして実践へと移し、実践結果をフォローし、再度診断を行っていく。これを定期的に繰り返しながら、学級を継続的に改善していくのである。
5. 若い教師へ伝えたいこと
これからの学級経営は「教師一人の仕事」ではない。学級診断ツールを活用しながら、データをもとに戦略的な改善を進めることで、教師の負担を減らし、子どもたち自身が学級づくりに関わる場を作ることができる。
また、「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」の視点を持つことで、学級の雰囲気を活発にし、子どもたちが主体的に動く環境を整えることができる。
若い教師には、データと協働の視点を持ち、学級経営を戦略的に進めることを意識していくことがこれからは求められる。
まとめ
学級経営の質を向上させるためには、
- 学級診断ツールを活用し、学級の状況を正確に把握する
- 2軸診断票とグラフ化で課題を可視化し、4象限に分類する
- 同僚や尊敬できる教師からアドバイスを受けながら、実効性のある改善策を決定する
- 「遊ぶように学ぶ 学ぶように遊ぶ」を学級づくりへ積極的に取り入れる
- 実践結果をフォローし、学級経営の質を継続的に向上させる
若い教師が学級経営を意図的・計画的に進め、データと協働を活用することで、持続可能な学級づくりが可能になる。もちろん学級は「生き物」であるから柔軟性や弾力的に対応することも必要である。この連載を通じて、その実践的な方法を示していくことにする。