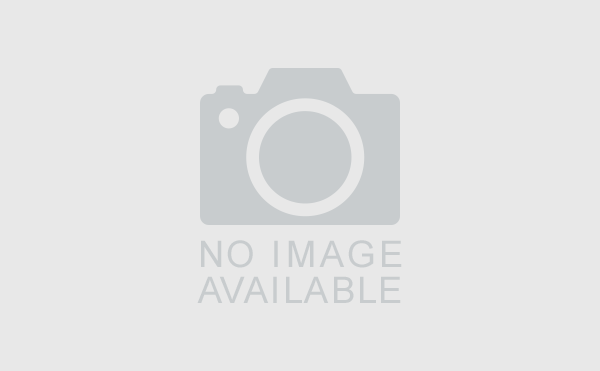【雑感】教師の教えることを否定しているのか
教師の教えるということについて、現場に誤解が存在する。
そのことについて前日のブログで触れた。
「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)」(平成29年12月21日中央教育審議会)では、どのように論じていただろうか。
まず、授業の質を工夫したり、改善することの意義が十分に理解されていないと「意味のある学びにつながらない授業になってしまう恐れ」があると指摘している。
例えば、どのような授業か。
「活動あって学びなしの授業」
「指導の型をなぞるだけの授業」
である。
「授業研究」の成果は、日本の学校教育の質を支える貴重な財産である。
○ 一方で、こうした工夫や改善の意義について十分に理解されないと、例えば、学習活動を子供の自主性のみに委ね、学習成果につながらない「活動あって学びなし」と批判される授業に陥ったり、特定の教育方法にこだわるあまり、指導の型をなぞるだけで意味のある学びにつながらない授業になってしまったりという恐れも指摘されている。
そして、次の懸念があることを述べている。
「狭い意味での授業の方法や技術の改善に終始する」
だからこそ、本来の目的を見失わずに授業の工夫や改善を求めている。
指導法を一定の型にはめ、教育の質の改善のための取組が、狭い意味での授業の方法や技術の改善に終始するのではないかといった懸念などである。我が国の教育界は極めて真摯に教育技術の改善を模索する教員の意欲や姿勢に支えられていることは確かであるものの、これらの工夫や改善が、ともすると本来の目的を見失い、特定の学習や指導の「型」に拘泥する事態を招きかねないのではないかとの指摘を踏まえての危惧と考えられる。
その上で、学習指導要領等が目指すのは、「自信を育み必要な資質・能力を身に付けていくことができるようにすること」である。
学習指導要領等が学習・指導方法について目指すのは、特定の型を普及させることではなく、後述のような視点に立って学び全体を改善し、子供の学びへの積極的関与と深い理解を促すような指導や学習環境を設定することにより、子供たちがこうした学びを経験しながら、自信を育み必要な資質・能力を身に付けていくことができるようにすることである。
そのために子どもの実態や教材等に応じて、研究を重ね、適切な方法を選択し、工夫して実践することを教師に求めている。
学びを実現する具体的な学習・指導方法は限りなく存在し得るものであり、教員一人一人が、子供たちの発達の段階や発達の特性、子供の学習スタイルの多様性や教育的ニーズと教科等の学習内容、単元の構成や学習の場面等に応じた方法について研究を重ね、ふさわしい方法を選択しながら、工夫して実践できるようにすることが重要である。
「主体的・対話的で深い学び」の実現は、特定の指導方法を指しているのではない。
「主体的・対話的で深い学び」の実現は、教員の意図性を否定するものではない。
教員には、教えることにしっかり関わってほしい。
「必要な学びの在り方」を考え、授業の工夫・改善を重ねていってほしいということを述べている。
「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、特定の指導方法のことでも、学校教育における教員の意図性を否定することでもない。人間の生涯にわたって続く「学び」という営みの本質を捉えながら、教員が教えることにしっかりと関わり、子供たちに求められる資質・能力を育むために必要な学びの在り方を絶え間なく考え、授業の工夫・改善を重ねていくことである。
以上の記述からわかるように、「教師は教えるな」なんてことは言っていない。
逆に、子どもの学びの質を深めていくために、教師は教えることにしっかり関わってほしいと言っているのである。
大切なことは、子どもの学びの質を深めていくことだ。
教師は、教えることへの懸念を踏まえつつ、目の前の子どもの学びを少しでも深めていくことなのだということを今一度再確認したい。